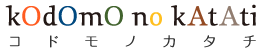4. 子どもの時間

―中瀬幼稚園では、活動と活動がつながっていて、子どもの時間が分断されていないように思います。日々の活動をすすめる上で大事にしていることを教えて下さい。
井口:子どもの生活を分断しちゃいけないですよ。それは当然のこととして考えています。
子どもたちの会話や動きの中に糸口を見つけながら、子どもたちの興味にあわせたことをしているだけです。もちろん、保育の方向性は持ちつつですが。
何気なく過ごすんじゃなくて、いつも子どもたちの行動の先にこういうことが起こるだろうと予測していますね。例えば、冬になるといつも園庭で焚き火をしているのですが、その燃料のために、みんなで枝を集めるんですけど、枝を拾えば、枯れたものと生のものとがわかるだろうし、皮の丈夫なものと丈夫じゃないもの、太さとか重さとか匂いだとか、いろんなことが身体の実感を伴ってわかります。扱い方も、こうしたら危険とか安全とかもわかりますね。もちろん、危ないこともありますから、言葉のかけ方に気を配りながら、繰り返し声をかけます。そうしていれば、子どもたちは自然と気をつけるようになりますし、子ども同士で学び合うようになります。
畑での野菜の栽培なんかも、虫に食べられちゃったとかカラスに食べられちゃったとか、順調にいく事ばかりではないですね。でも、そういうことこそ重要で、ちいさな出来事を「なんでだろう?」「どうしたらいいだろう?」って、自分の頭で考えたり、子ども同士で相談したり、協力しあったりする。そういうちいさなことを解決していくところに、子どもたちの成長があるのではないでしょうか。
―子どもたち自身で考えるように、大人は寄り添うということですね。
井口:そうですね。教えるのは簡単なんですが、そうでない言葉をかけるのは、とても難しいですね。でも、いつも言葉に注意を払っていれば、子どもたちは自ら考えるようになります。そのためには、わかりやすく、子どもたちが受け入れやすい言葉を見つけなければいけません。保育の中で、言葉は本当に重要だと思います。
今日、畑でピーナッツの種を蒔いたんですけど、以前蒔いた種がカラスに食べられてしまったんですね。だから、カラスに食べられないように蒔きたいとみんな思っているわけです。そこで「カラスのくちばしはどのくらいかな?」と言葉をかけたら、みんな自分の経験を総動員してカラスのくちばしの長さを考えるわけです。それで、くちばしが届かないように深く蒔いたらいいんだと気付く。細かいところをおもしろく伝えると、子どもたちは興味をもっていくんですね。そのためには、子どもたちの生活から離れない、具体的に想像できる言葉が必要だと思います。