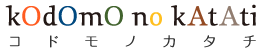3. モノ言えぬ子どもたちのために

―中瀬幼稚園には、行事がほとんどないですね。幼児教育全体としては、
園の特色を出すために、行事を増やしたり、園内でのお稽古事を増やしたりという傾向があるように思うのですが、その点についてはどのようにお考えですか?
井口:運動会をやったり、お遊戯会をやったりすることで、子どもたちが、さも何かができるようになったと思ってしまう。そういうわかりやすい「見せる保育」をすることは、本当の意味で子どものためになってはいないと思うんですね。運動会で何か訓練をしたり、劇ごっこをしたり、みんなで協力しあってやりました、というのは非常に消極的、受動的なものだと思うんです。子どものことを知らないから、見せるために力を入れてしまうのではないでしょうか。
行事に追われて、若い先生たちが子どもたちとの関わりを楽しめなくなっていることにも危惧を覚えています。映画「風のなかで -むしのいのち、くさのいのち もののいのち」の上映会後のお話会で、ある幼稚園の園長先生に「どうしてこんなに子どもたちの言葉が豊かなんですか?」と質問を受けたんですけど、「余計なことをやっていないからです」と答えました。本当にそう思うんですよ。幼児教育に携わる人たちは子どもを見ることから、もう一度はじめるべきだと思います。
活動に余裕がなかったら、アップアップしてしまって、子どもをゆっくり見つめることなんてできません。子どもたちの言葉や行動の中に、たくさんの発見が得られる環境をつくることです。しかし、のんびりしていたからといって、発見があるわけではないので、やはり保育者の意識が重要になってきます。
―映画「風のなかで」を制作しようと思われたきっかけを教えてください。
井口:幼児教育について「自然の中で、豊かな感性を」などと皆さん、おっしゃっていますが、現状はそれとは逆の方向へと流れていて、大人にとって都合の良い制度ばかりが取り沙汰されています。子どもたちはわたしたち大人が考えている程、幼くはありません。純粋な部分ばかりではありません。したたかで、逞しくもあります。でも、子どもたちは伝えることができないから、かわりに子どもの生の姿を伝えなければと思いました。わたし自身、子どもたちのふとした姿や言葉にふれた時、いままでの見方、考え方が少し修正されたり、新しい見方を見つけたりして、自分の世界が広がったようで嬉しくなります。そうした喜びも含め、映画を通して伝えられたらと思いました。